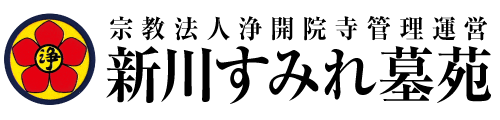すみれ墓苑は


モノレール延長建設によるお墓の立退き、お墓の移転をお考えの方、南風原町・那覇市にお住まいで、生前墓地や分家等で新たに建立をお考えの方、首里石嶺・南風原町近隣でお墓をお探しの方は、ぜひ一度すみれ墓苑をご見学ください。
また、管理型墓苑なので安心・綺麗な状態でいつでもお参りが出来ます。
新着情報
宗教法人浄開院寺は
みんなのための、みんなのお寺を目指しております。
小さなお寺では御座いますが、思いやり、支え合い、携え合って生きる場所、そんな拠り所をつくりたいとスタートして早20年が経ちました。北谷町でプレハブのお寺から始め、宜野湾市大山に移転(寺)しましたが、宗教活動も信徒が増え手狭になりましたので浦添市内間の民家を購入して改装し、お寺をつくりました。
御本尊は、不動明王を台頭に観世音菩薩、大日如来、地蔵菩薩、文殊菩薩、釈迦如来、勢至菩薩、千手観音、その他の仏像を祀り、日々研鑽修業の為、読経を唱え、仏の教えを学んでいます。 「みんなでつくる みんなのお寺」を合言葉に励み、みんなが喜ぶことを自分の喜びとして家族のように、親のように、友達のように接して、小さいながらも充実したお寺作りをしております。浄開院寺は若いお父さん、お母さんや赤ん坊、子供たち、年配者まで幅広い老若男女の人たちが集い笑いの絶えない明るいお寺です。出会えてよかったと思うお寺、生きる喜びがわくお寺、苦しみを乗り越えた仲間がいるお寺、元気の出るお寺、感謝の心がわくお寺、仏さまを感じる清らかな空気のあるお寺、垣根のない、そんな「みんなのためのお寺です」です。あなたも仏様のご加持のもとで安心のある生活しませんか。

仏教との出会い
私は、会社経営をし、毎日毎日家庭を顧みず、がむしゃらに働いていました。
家庭のためになると思い、朝から晩まで働いていましたが思うようにいかず、日々悶々とした生活を続けていました。心の苦しみを消化できない私は、ありとあらゆるお寺の門を叩いて回りました、しかし、話を聞いてくれるお寺がなかなか見つかりませんでした。
近くにお寺があることを思い出し、そのお寺を訪ねました、ご住職が気さくで優しく私の話を聞いてくれました。
そしてそのお寺に通うようになり、勉強会にも参加しました。 不動明王を台頭に観世音菩薩、大日如来、地蔵菩薩、文殊菩薩、釈迦如来、勢至菩薩、千手観音、その他のご本尊様と、であうことが出来ました。
人生をリセットする
私は30代半ばになって、意を決して仏門の世界に入りました。
いろいろな仕事を手がけましたが、何一つうまくいきませんでした。
借金を抱えて生活が苦しくなるばかりでした。
何をやってもうまくいかないのは、自分の生き方が間違っているかも知れないと思い、自分が培ってきた、概念や価値観を捨て人生をリセットして見ようと決心しました。
未練を持たないために、たくさん持っていた本や衣類や持ち物を捨て、修行に必要な分だけの身となって、瞑想をし、修行三昧の日々を過ごしている時、深夜に突然不動明王が現れて、御真言を唱えている声が脳裏に聞こえました。そして頭から何かが体に入ってきたのです。それから私は、不動明王様が力を下さったと信じ私は、無我夢中で修行に励みました。そしてある日の夜、人助けをするようにと告げられたのです。
宗教活動を開始
北谷町のプレハブのお寺から、人助けが始まりました。
人助けといってもほとんどが家庭の悩み、先祖事の悩み、葬儀、法事、地鎮祭、水子供養、お祓い、その他、お客様のすべての悩み事の相談、アドバイスをしております。
お客様から、お客様を紹介して頂き人が集まるようになりましたので、宗団をつくることにしました。
ガラス張りの宗教団体を目指し、「みんなのためのお寺」「みんなでつくるお寺」を意識して、それぞれが役割をもってお寺の運営にあたるようにしました。
ちっぽけなお寺ですが、伝統仏教を大切しながら、沖縄の風習も大切にしながら、敷居の低い、開かれた「みんなのためのお寺」つくりは健在で奮闘中です。
仏様の教え
大乗仏教では自ら積んだ功徳を他の人々にふりむけること(回向)が要請されています。
供養の本当の意味
功徳は、善い行いをすることによって、神仏から目に見えないが、徳性が与えられると考えられます。この特性を他に振り向けることによって、自分自身も他も(目に映らない世界のものも含む)仏果を成就しようとする行為が供養の本当の意味になるのではないでしょうか。
ここで善い行いとは、どんな行いでしょうか。それは、あくまでも仏の教えを守り実践することにほかありません。
浄開院寺では、これらを踏まえて次の三つの供養を奨励します。
一、仏様の供養 二、先祖の供養 三、自分の供養
三番目の自分の供養について不思議に思うかもしれませんが、実は私たち自身の内に仏を宿しているのです。しかし、煩悩に覆われて本当の姿が見えないだけです。
供養することによって、本来の光輝く仏の姿が現れてくるかもしれません。仏道を歩み功徳をめぐらして自分も他も利する人物になりましょう。

水子供養
(完全予約制です・時間をお守りください)
水子の供養は大切です、いかなる理由があるにせよ、この世に生まれたかった命です。お母さんに抱かれて幸せになりたかったに違いありません。やむを得ない理由で、命が失われるのは本当に悲しいことです。
浄開院寺では、塔婆を立て懇ろに供養いたしますのでご安心頂けると思います。
*お寺は生命の大切さを教える所です、決して堕胎に賛同するものではありません。堕胎を前提に事前予約をしようとする方がおりますが、考え直して下さい。そのような予約は一切お断りいたします。
水子の災い
供養が十分されていないと、後々さまざまな災いに悩まされることがあります。
特に女性には、激しい頭痛、腰痛、生理不順に悩まされたりします。成長した子供にもいろいろな出来事が起こることもあります。
もし、病院で分からない病気に悩まされていたら、お寺に相談してください。
「すくわれた人はたくさんいます」

法務内容
- 葬式/告別式
- 法事の相談(年忌法要予約)
- 仏壇・遺骨・位牌一時お預かり・永代供養
- 地鎮祭(住宅・墓地等)
- 各種祈願(健康祈願・交通安全・学業・安産・家内安全等)
- 水子供養
- 開運厄徐お祓い(厄年のお勤め)
- 各種人生儀礼の勤行
- 人生相談 悩み(親戚・近所・介護・いろいろな悩み事相談)
- 仏壇・遺骨・位牌に関する相談
お寺に通う習慣
お寺に通う事を心がけると、知らず知らずのうちに、心が癒され、迷いを打ち消し安心を得た生活を営むことが出来るようになります。
法要について
法事(法要)とは、身内などの親しい人たちが集まって、故人の冥福を祈り、その霊を慰める仏教的な儀式をいいます。七日目(亡くなった日も含む)に行われる「初七日」や「四十九日法要」、1年後の「一周忌」などを区切りとなる日に行われます。
追善法要
亡くなられて、次の世に生まれ変わるまで七日間を七回くりかえすことが必要だとされております。そして四十九日になりますと満中陰といって死者が浄土にいかれたといいます。この日は遺族と親類・故人と親しかった知人・友人が菩提寺の僧侶を囲んで法要を営みます。
仏教では、人が亡くなってからの7週間は、7日ごとに死後の世界の裁判官である閻魔(えんま)による生前の功徳(くどく)に対する裁判が行われるとされています。そこで故人の霊が無事、極楽浄土に行くことができ、成仏するようにと7日ごとに供養されるわけです。
| 種 類:亡くなられた日から数えた日にち | 教え |
|---|---|
| 初七日(しょなのか):七日目 | 秦広王(しんこうおう)・不動明王(ふどうみょうおう) 死者が三途の川のほとりに到着する日であるとされています。川の流れが緩やかなところを渡れるように願って営むのが初七日法要です。 |
| 二七日(ふたなのか):十四日目 | 初江王(しょこうおう)・釈迦如来(しゃかにょらい) 故人の善いところを振り返るとき |
| 三七日(みなぬか):二十一日目 | 宋帝王(そうていおう) 文殊菩薩(もんじゅぼさつ) 自分自身の生き方を懺悔する |
| 四七日(しなぬか):二十八日目 | 五官王(ごかんおう) 普賢菩薩(ふげんぼさつ) 亡き人と同じ思いになり故人の願いを考える |
| 五七日(ごしちにち):三十五日目 | 閻魔王(えんまおう) 地蔵菩薩(じぞうぼさつ) 悲しみの中にもう1度初七日の心を思い出し自分を磨くと誓う |
| 六七日(むなぬか):四十二日目 | 変成王(へんじょうおう) 弥勒菩薩(みろくぼさつ) 自分のことだけではなく故人のその周りの人の悲しみも思いやりましょう |
| 七七日(しちしちにち):四十九日目 | 太山王(たいせんおう) 阿弥陀如来(あみだにょらい) 故人に感謝し報恩の供養をこれからもすることを誓う |
| 百カ日(ひゃかにち):百日目 | 涙をそっと拭き泣くことを卒業しようと誓う |
年回忌法要について
一年目にあたる命日に一周忌、二年目には三回忌が行われます。下記の表のように五十回忌で終わりになります。一周忌は遺族や親族の他に、故人と親しかった方を招いて行いますが、七回忌からは身内のごく親しい親類縁者が集まり法事をとり行う傾向が高まっています。
| 種 類 | 亡くなられた年から数えた年 |
|---|---|
| 一回忌 | 1年目の祥月命日 |
| 三回忌 | 2年目の祥月命日 |
| 七回忌 | 6年目の祥月命日 |
| 十三回忌 | 12年目の祥月命日 |
| 十七回忌 | 16年目の祥月命日 |
| 二十三回忌 | 22年目の祥月命日 |
| 二十七回忌 | 26年目の祥月命日 |
| 三十三回忌 | 32年目の祥月命日(この法要をもって弔い上げとすることが多い) |
| 五十回忌 | 50年目の祥月命日 |
仏教では、亡くなってから33年経つとどんな人でも無罪放免となり、極楽浄土に行けるとされています。 合掌
ご相談
葬儀や法事(年忌、地鎮祭、永代供養、ペット供養、位牌や墳墓移動、販売等)他各
ご相談も受け付けています。
ご相談、ご質問・お問い合わせはこちら
下記の電話番号または、お問い合わせフォームからお願いします。
注:住職法務の場合、寺不在のため夕方以降及び後日になることがあります。
法事に関するお問合せ
090-1345-8447

お墓に関するご要望090-1345-8447受付時間 9:00-17:00
お問い合わせ